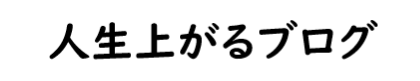どうもagaruです。
問題解決力アップのための記事第3弾です笑
前回までのあらすじは
ビジネス系のケース問題へのアプローチ方法がこちらの記事。
どうもagaruです。コンサルを転職の可能性の一つとして考えていた時に、問題解決のための手法を学ぶべく少し勉強しました。ケース面接で、『ビジネス系問題ってどうやってアプローチしたらいいの?[…]
特定した問題への原因の掘り下げ方がこちら。
どうもagaruです。以前、問題解決のために、問題の本質をとらえる記事を書きました。[sitecard subtitle=関連記事 url=https://www.agaritaiblog.com/c[…]
今回は、掘り下げた原因と問題の因果を正しくとらえられているかを
確認する方法についてご紹介いたします。
因果を正しく考えられたか確認する
原因の追究の流れはこのようになっています。
因果の構造図で、深く広く掘り下げる。
↓
因果を正しく考えられたか確認する。(今回のテーマ)
↓
手を打つ場所を決める
ここまでで、原因分析を正しく行えていたとしましょう。
この因果の正確さを確認する術を紹介します。
因果の構造図の見た目で判断
一番単純な方法は、見た目です。
1.一直線
2.末広がり
3.気球
一直線型
これは、「なぜなぜ」を置くなう際に
一直線に深堀していくことを指します。
「原因はきっとこうだ」といった原因の決め打ちをすると
このような結果になることがあります。
末広がり型
因果の構造図をしっかり幅広く考察できたとしても、
ロジックツリーのように広がりっぱなしになっている状態を指します。
ここで注意したいのは、根本原因がそんなに多数あるというのは考えづらいということです。
事実ではないものを消し込んだか
たまたまのものを省いたか
どうしようもないもので打ち止めしたか
こういったものをきちんと絞らず悪循環を生んでしまうと
広がりっぱなしといった状態になってしまうのです。
事実による消し込みと打ち止めを意識して防ぐよう意識しましょう。
気球型
こちらは広がりっぱなしの「末広がり」と逆のパターンです。
問題の深堀の出だしはうまくいっているのに
最後、突然に1つの根本原因に集約されてしまうようなケースをさします。
検討時間を十分とれず、無理やりまとめにいくと
こういった構造図ができてしまうのです。
1段目と2段目の抜け漏れをチェック
「1段目」:
WHEREで特定した最初の原因
「2段目」:
1段目の次の原因
この2か所に抜けがないかをチェックすることが重要です。
例えば、
売上=販売数×単価
とした場合に、
「売上」の問題について考えようとしているときに
「販売数」しか原因にあげていないとすると
「単価」についての要因をすべて漏らしてしまうことになります。
このように掘り下げの1段階目での抜けというのは
全体の完成度に大きく影響してしまうのです。
1番下が打ち止めになっているか確認する
先ほどが、因果の上の部分を確認するとすれば
次は下の部分を確認する術を説明しましょう。
打ち止めに関する部分です。
因果の構造図は最終的には少数の原因に収束する必要があります。
1つ1つ原因を見ていきましょう。
必ず、矢印でつながっているはずです。
ここで矢印がない丸印は
「事実でない」
「どうしようもないもの」
「たまたまやっていないもの」
これらに該当するはずなのです。
ここで、因果の構造図を書き上げた後に
一番下に来ている丸印が本当に打ち止めとなっているのか再度確認しましょう!
上記3つに該当していなければ、
まだ掘下げの余地があるかもしれません。
「さらなる深い原因」を見落とさないよう打ち止めの確認が重要なのです。
問題の固有原因になっているか確認する
1つ事例をあげましょう。
あるアミューズメントパークでの問題に対し、掘り下げを行いました。
「平日夜のカップルの客数が減っている」
↑
「来ようと思わなくなった」
↑
「交通の便が悪くなった」
↑
「車で行きづらくなった」
↑
「駐車するスペースが減った」
↑
「不要な建物を建てた」
一見、客数が減った原因としては、「不要な建物を建てた」というのは
原因になっているように見えます。
しかし、これは「固有の原因」でしょうか。
答えはノーです。
最初の問題は、「平日夜」という部分はどうでしょうか。
駐車スペースがないことは
「休日」にも影響しますよね?
これは固有原因とはいえません。
この固有原因を探ることが、真の問題解決につながる原因を洗い出す最善策なのです。
さいごに
原因を掘り下げるだけでは、
原因追及の半分もこなせていないのです。
今回の因果の確認を経て、
やっと追及していくべき因果を設定できます。
コンサルの論理的思考は、こういった理屈を徹底していった先にあるのでしょう。
どうもagaruです。 今回は、『コンサル業界への転職』を考えている方向けに私の体験談をお話します。 事業会社に勤めていた3年前に、[…]
ではまた。