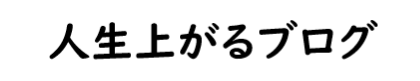どうもagaruです。
少し前から、
電力需給ひっ迫のニュースや電力会社の周知を見る機会が増えました。
これって、
単に日本が今年寒かったからなんでしょうか?
結論から言うと
私は、原因の根っこは電力自由化による弊害だと考えています。
あまりニュースで、その点については報道されなくなっているので
少し裏話を混ぜてお話いたします。
電力自由化前の電力需給はひっ迫していたのか?
今年の冬は、寒波の到来が例年に比べて早かったのは
周知の事実でしょう。
しかし、
早期の寒波によって、暖房使用などから電気を消費する機会が増加し
電力需給がひっ迫するほど、暖房器具を使用するでしょうか。
答えはNoです。
以前の電力業界であれば
難なく処理したレベルの寒波です。
では、なぜ今回はだめなのか?
答えは、電力自由化による業界の不安定さがようやく明るみに出たからです。
電力需給がひっ迫してしまう電力自由化のデメリットとは。
昨年のコロナウイルスの感染拡大に伴い
電力消費の量は大きく下がり、電力会社は、あまりに余ったLNGの処理に追われました・・・
そこで、電力会社はロスを少なくするように余分な燃料を仕入れないようになりました。
また、再エネも天候の影響であまり発電ができていない状況でした。
そんなとき
寒波が予想よりも早く来たため
暖房器具の使用が増えてしまい、急遽電力需給バランスがくずれていきます。
通常、
電力需給を調整するのは電力会社の火力発電所ですが燃料不足で追いつきません。
案の定、電力が足りない事態となりました。
原子力がほぼ稼働していない現状で、
・火力発電の割合を減らし、再エネの割合を急速に増やしたこと
・自由化により、発電から需要家までの流れについて責任が曖昧になったこと
一元管理は、迅速な対応を可能にします。
これが原因でしょう。
電力会社が単独で発電量と需要のバランスを見ていた時は
電力会社内で調整が効いていましたが、
国内の電力需要に対して、電力会社が供給する割合が下がっている現状では
バランスを取ろうにも電力会社に余力がない状態となっています。
結果、海外と同様に電気代は上昇していく傾向になりました。
電力自由化の政策は
はたして国民のためになっているのかは正直疑問です。
さいごに
電力業界については
菅首相のカーボンニュートラル発言から
・進捗が芳しくない原子力発電
・ベースロードにするには時期尚早な再エネ発電
この二つの大きな課題を抱えたまま、
毎年電力需給ひっ迫の憂き目にあうことになりそうです。
今回の件を経て、
電力統合の流れになるのであれば
自由化っていったい何だったのかと考えてしまいますね・・・
それでは今回はこの辺で!
ではまた!!