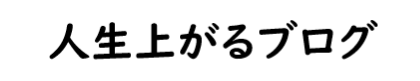私が近々で勤務していた半導体メーカーでのお話です。
私は、電力会社で働いた後、
大手の半導体メーカーにて、パソコン用のディスプレーやビジネスプロジェクターなどを開発するエンジニアとして働きました。
そこで、今話題になっている半導体関係の専門職の方と話す機会がありました。
その方の技術としての担当は電気関係で、デジタル回路設計が専門でした。
でも、その仕事は、今ではしていません。
それは、その需要がなくなってしまったからです。
今回は、半導体に関わる仕事を通じて
についてお話いたします。
半導体メーカーの先輩社員が専門だった技術内容
話は10年くらい前に遡りますが、
彼はデジタル回路設計の最高峰と言われる超LSIに関する、論理回路設計エンジニアでした。
20年ほど前はデジタル回路も回路図入力をしていましたが、
10年ほど前にはVHDLという特殊な論理記述言語を使用して、大規模LSIを設計できるエンジニアとして働いていました。
回路図入力時代には一人の設計限界は10万ゲート(約20万個のトランジスタを使用する規模)、
言語設計になってからは一人で100万ゲートを設計することもざらになりました。
LSIを自社設計するメリットは、他者との差別化ができることです。
特許技術をエンジニアが考えて、その回路をLSIに組み込むことで、他社ではできないような新機能を実現するわけです。
誰でも、知っているようなLSIの一例を挙げると、キヤノンさんの「DIGIC」などがあります。
キヤノンさんは、DIGICを搭載して他社にはない高画質を実現していますよね。
突然半導体設計業務がなくなった
これは、今から9年ほど前のこと、上司に呼び出され突然「我が社では半導体設計を撤退する」と言われました。
その理由は以下3点でした。
①半導体設計の開発費を捻出できない
②自社開発の半導体よりも汎用半導体の方が安くセット価格を安くできる
③現在は新機能よりも安い製品を顧客が望んでいる
①については、最近の半導体の微細化技術の急速な進歩と、
設計する回路の規模の増大により、かつては半導体の開発費用が500万円程度だったのが、5,000万円から1億円まで高騰していたのが理由です。
自社にて半導体開発をすると開発費を販売台数で割った数字と、
半導体の製造コストを足したものが半導体単価となるので、
②のように大量の販売数を誇る汎用半導体メーカーのような安いチップ単価も実現できません。
③については、台湾メーカーが出すあまりにも安い製品のせいで、
国内製品も影響を受け、プライスダウンのためのコストダウンに体力を使うがあまり、
エンジニアたちが新機能を考える時間がなくなってしまったことも要因です。
この時には、うちの会社もこれから競争に負けてもっと赤字になるのだろうなと思ったそうですが、
今振り返ってみると、同等製品を作る他社も同じ方針を取り始めていて、
大手のパナソニックや、エプソン、日立なども同じ道を辿っていきました。
消費者の価格へのこだわりと、韓国勢の安価モデルの進出が日本に与えた影響
我々の業界の例で紹介すると、完全に他社との差別化要素がなくなりました。
異なるのはデザインのみで、性能は全く同じなのです。
それもそのはずです、どのメーカーも韓国のサムスン電子の液晶パネルを採用し、
ピクセルワークスという汎用半導体を設計する画像よりエンジンを搭載しているのですから。
このような動きは、電気業界ではパソコンから始まりました。
DOSVマシンの登場以降は、どのメーカーも同じCPUを採用し、
グラフィックチップなども同じものを採用していて、異なるのはやっぱりデザインと、プリント基板のレイアウトくらいです。
今はどこのメーカーのパソコンを買っても機能が同じことは多くの消費者が感じているのではないでしょうか。
残るのは品質くらいです。
そして、エンジニアたちにとっては、会社にとっては技術力は必要ないため、リストラされることが多くなりました。
彼の場合も、エンジニアとしてではなく、今では、ほぼほぼ事務職として働いています。
今後の消費者に半導体メーカー社員が望むこと
今現在働いている私の目から見て、日本の技術の空洞化は深刻なほど進んでいると感じます。
会社ではリストラされることも多いですが、
先を見越せる優秀なエンジニアたちは、韓国の企業に転職するなど、優秀な日本の人材が海外に持っていかれているのが現状です。
日本の技術力が落ちてしまうだけでなく、海外の技術力を日本人が持ち上げている状態になり始めています。
世の中が不景気であることも理由ですが、
私が考えるところ、消費者の低価格へのこだわりが招いた惨事でもあると考えています。
確かに、最近は、ネット通販などで価格競争に目が行きがちですが、
技術大国日本をもう一度散り戻すためにも、
価格よりも性能にこだわりを持って商品選びをする
ちょっとゆとりのある考え方をしてほしいと真に願っています。
では今回はこの辺で。
ではまた!!