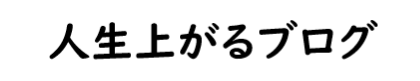どうもagaruです。
今回も問題解決力アップの記事となります。
これまで
ビジネス系のケース問題へのアプローチ方法がこちらの記事。
どうもagaruです。コンサルを転職の可能性の一つとして考えていた時に、問題解決のための手法を学ぶべく少し勉強しました。ケース面接で、『ビジネス系問題ってどうやってアプローチしたらいいの?[…]
特定した問題への原因の掘り下げ方がこちら。
どうもagaruです。以前、問題解決のために、問題の本質をとらえる記事を書きました。[sitecard subtitle=関連記事 url=https://www.agaritaiblog.com/c[…]
正しく掘り下げれたかの確認方法がこちら。
といった流れでご紹介してきました。
今回、実際に特定した原因たちの中で、どのような仕手をうつか、どこにうつかについてご紹介します。
問題を解決するために、手を打つべき原因を明らかにする
さて、これまでに順調に原因分析までが行えたとしましょう。
ではどこに手をうつべきか
結論から言うと
まずは<問題解決の効果を高める>
・「主たる原因」に手を打つ
・全体に影響が出るように手を打つ
・浅すぎず深いところに手を打つ
・立場とリソースを考え分担しながら手を打つ
そして<対策の実現性を高める>
・「単にやっていないだけの原因」に手を打つ
・「入ってくる矢印が少ない原因」に手を打つ
・「下にある原因」に手を打つ
最後に<検討の効率を高める>
・悪循環を断ち切るように手を打つ
・いくつかの原因にまとめて手を打つ
さて、それでは順番に説明していきましょう。
問題解決の効果を高める
「主たる原因」に手を打つ
ある問題に対して複数の原因が考えられる場合、
すべての原因が同じように作用するとは考えにくいです。
数ある原因で中には、特に強く影響している原因、いわゆる主たる原因が存在します。
この主たる原因が何なのかをしっかりと見極め、
そこに手を打っていくのが最も基本的な考え方となります。
いくつかの原因を見比べ、
原因として大きく効いているものを見極め、手を打つことが重要なのです。
全体に影響が出るように手を打つ
例えば、アミューズメントパークの売上が低下している場合、
単価と、来客数の両方に影響している原因に手を打つことが一番影響が大きいのです。
浅すぎず深すぎないところに手を打つ
なぜなぜ分析の際には、打ち止めになるまで原因を掘り下げますが、
打ち止めとなるような深いところに手を打つのが良いかというと
必ずしもそうではないのです。
例えば、「メーカーの新製品が売れていない」として、
一番深い原因に「営業部門の意識を改革する」という仕手をうつとします。
どうでしょう?
すごく時間がかかるような気がしませんか?
これはおそらくその通りです。
問題解決には、いつまでに~という制約がつきものなのです。
中長期を視野に入れるなら、深いところ。
短期的には浅めのところに手を打つのが定石と言えるでしょう。
立場とリソースを考え、分担しながら手を打つ
さて、いくつかの手を打つべき箇所を説明しましたが、
何個くらい手を打つのが良いのでしょうか?
全ての原因に手を打つのは現実的ではありません。
ここで心に置きたいのは
「自分自身の立場とリソースを踏まえて、どこまでに手を打てるのか考えてほしい」
ということです。
さらに言えば、たとえ、担当レベルで裁量に限度があっても
他者を説得し、動いてもらうのが、分担しながら手を打つということなのです。
問題を解決するために対策の実現性を高める
続いては、実際にどの原因に手を打つのかということです。
「単にやっていないだけの原因」に手を打つ
このような原因があるのはラッキーです笑
長年の問題には「単にやっていないだけ」という原因はほぼないですが、
もしあれば、即座に手を打てる対象として非常に便利です。
「入ってくる矢印が少ない原因」に手を打つ
これまでの話では、
矢印の多く入ってくる主たる原因や、単にやっていないだけの原因について
手を打ってきました。
しかし、入ってくる矢印が少ないが、出ていく矢印が多い原因というものであればどうでしょう?
手を打つことで、より大きな影響を与える可能性があるのではないでしょうか。
こういったものにも手を打つのが更なる対策の実現性を高める要素となるのです。
「下にある原因」を避けて打つ
一番下の原因が、人のせい・環境のせい、であるので
どうしようもないと割り切るしかない場合には
その一つ前の原因に手を打てないか探るのです。
どうしようもない原因について手を打つのはナンセンスですが
手を打てそうな一つ上の原因へアプローチすることで問題解決にすこしでも
近づくことが重要なのです。
問題の解決の際には検討の効率を高める
悪循環を断ち切るように手を打つ
悪循環の例を挙げると
売上が低下している
↑
お客様を呼び込めていない
↑
店構えが古びている
↑
改修する予算がない
↑
予算がないのは利益が低下しているから
このような悪循環があるとします。
もし、ここで「お客様を呼び込む」という手を打ったとすると
この循環は好循環へと変化するのです。
このように、悪循環を断ち切ると好循環を生むことがあるのです。
いくつかの原因にまとめて手を打つ
「新製品の販売数が伸びない」
↑
「新製品がお客様に認知されていない」
↑
「営業が新製品の説明をおこなえていない」
↑
「営業に新製品の知識がない」
↑
「営業教育が不足している」
このような事例があったとしましょう。
更なる原因として
「営業が新製品の説明をおこなえていない」
→「プレゼン能力が低い」
「営業に新製品の知識がない」
→「営業現場で使える販促資料がない」
があったとしましょう。
ここで
「プレゼン能力の低さをカバーする販促資料をつくる」
と手を打ったらどうでしょう。
このようにまとめた対策で一網打尽にできるのです。
考えるべきことは、
「まとめて一網打尽に手が打てる原因はないか」
を常に探すことなのです。
さいごに
さてどうでしたでしょうか?
今回は
深堀りした問題に対して、どのように原因を追究して、解決していくのかという手段について
ご紹介いたしました。
コンサルの理詰めの考え方については
こちらの議事をご覧ください。
どうもagaruです。 今回は、『コンサル業界への転職』を考えている方向けに私の体験談をお話します。 事業会社に勤めていた3年前に、[…]
ではまた!